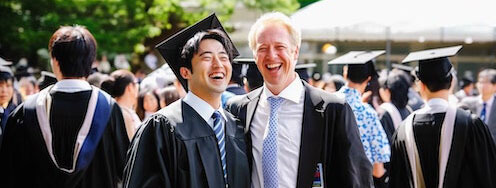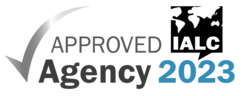インターンシップするなら、日本?それとも海外?
2025年度の就職活動は、引き続き学生が売り手市場と言われており、2024年3月卒業予定者の内定率は2024年2月時点で全体8割弱と半数を超えています。新卒採用市場では優秀な人材の争奪戦がますます激化し、採用選考活動のより一層の早期化が叫ばれています。そうしたなか、企業としても採用広報が解禁する前に、より良い人材を確保するためにさまざまな取り組みを行っています。その一つが「インターンシップ」です。
「就活に有利」「就職に直結する」などのイメージから、インターンシップに興味を持つ学生は多く、それは海外留学を考える学生も同様なようです。海外の企業でインターンをすることが、その後のキャリアにプラスになるのではないか.. その考えは間違っていません。しかし、就職活動のスケジュールを踏まえると、日本と海外、どちらでインターンに挑戦・参加するか悩む方もいるようです。
そこで、今回は、インターンシップの目的や日本と海外とで異なるインターンシップのあり方などを踏まえ、日本と海外、どちらでインターンに挑戦・参加すべきか、解説していきます。
1:日本における就職活動とインターンシップの現状
2:本来、インターンシップの目的とは
3:日本と海外、「インターンシップ制度」の違い
4:正解は海外インターン→日本でのインターン
5:世界有数のダイバーシティ オーストラリア・シドニーで開催される海外インターンシップ
6:海外インターンシップ参加者体験談【動画】
1:日本における就職活動とインターンシップの現状
2025年度の就職活動は、前年度に引き続き、学生優位の「売り手市場」が続いています。2024年3月卒業予定者の内定率は2024年2月時点で77.0%に達しています。内定出しのピークは4月下旬ではあるものの、実際には12月以前に内定を出す企業が1割を超えるなど、例年より早期の内定獲得が進む傾向が見られます。
一方で、企業側は採用状況に必ずしも満足しているわけではありません。「質・量ともに満足」と回答した企業は24.2%とわずかに増えたものの、「質・量ともに不満」と考える企業も増加しており、企業側の採用満足度は依然として低い状況です。特に「採用数(量)」への不満が多いことから、企業は選考基準を下げずに優秀な人材を確保しようと、学生の獲得競争が激化していると考えられます。
このような背景から、企業は採用広報の解禁前に優秀な人材を確保するため、インターンシップに力を入れています。2023年度にインターンシップを実施した企業は76.2%に増加し、注目度の高さがうかがえます。実施期間は「半日(57.4%)」や「1日(41.4%)」と、短期プログラムが主流ですが、2〜5日間の複数日インターンシップも増加傾向にあります。これは、企業が学生との関係構築をより深め、ミスマッチを防ぎたいという意図の表れと言えるでしょう。
参照:DISC 新卒採用に関する企業調査(2024年2月調査)
2:本来、インターンシップの目的とは
本来のインターンシップの目的は、教育的な観点に立脚しており、「学生が実社会における職業体験を通して、自己のキャリア形成や職業理解を深めること」にあります。これは日本・海外問わず、インターンシップの根幹にある目的です。
例えば、日本においても、「オープン・カンパニー」「キャリア教育」「汎用的能力・専門活用型インターンシップ」「高度専門型インターンシップ」と呼ばれる種類があり、短期的なものから長期的なもの、また、その目的も「個社や業界に関する情報提供・PR」といったものから「働くことへの理解を深めるための教育」というものまでさまざまです。しかし、日本では、採用に直接つながると期待して業務を全く体験しない「インターンシップ」と称する短期プログラムが多い傾向にあり、国際的なインターンシップと大きく乖離しているため、外国人留学生など海外の学生の理解や参加が得られにくいのが現状です。
参照:産学で変えるこれからのインターンシップ|産学協議会
一方、海外のインターンシップは、本来のインターンシップの意義を体現しており、実際の業務に触れ、仕事の実態を体験することで、教科書や座学では得られない知識を習得する「職業理解・業界理解」、コミュニケーション能力、チームワーク、課題解決力などのソフトスキル、業務に必要な技術やツールの初歩的な理解する「実践的スキルの習得」、大学や学校での学問的知識と、現実社会の実務との関係性を知る「学びと社会の接続」、自分の強み・弱み、興味関心、価値観などを仕事を通して見つめ直す「自己認識の深化」などを得ることができます。
結果、自分がどんな仕事に向いているのか、将来どうなりたいのかを具体的に考えるきっかけになり、自らのキャリアを主体的に選べるようになります。
参照:インターンシップの推進に当たっての基本的考え方
3:日本と海外、「インターンシップ制度」の違い

もう少し具体的に、インターンシップにはどのようなタイプがあり、日本と海外とではどう異なるのか、見てみましょう。
まず、インターンシップのタイプには大きく4つあります。
1. セミナー・見学型
期間:半日から数日間
内容:会社説明、店舗や工場などの見学、社員との対談
2. 課題解決型
期間:数日~1週間
内容:課題を与えられ、グループで相談しながら解決策を探る。結果をプレゼンしたり、評価で順位をつけたりする。
3. 採用直結型
期間:数日~数週間
内容:グループディスカッションなどの内容を採用選考の参考とする。実際に各部署に配属され社員と共に働く場合もある。
4. 職務実践型
期間:数週間~数か月間
内容:実際に各部署に配属され、実務を体験する。取引先を訪問したり、企画を立案したり、社員と同等の立場で職にあたる。
日本の企業の場合は1、2、3のインターンシップを実施している企業が多く、海外の場合は4のタイプを実施しているところが多いです。
日本のインターンシップの場合、会社の雰囲気や就労の様子を垣間見ることはできても、自分自身が実際に業務に携わったり、社員との人間関係の構築などにつながったりすることはなかなかありません。対して海外のインターンシップの場合、実際に責任をもって就労にあたり、「社会人として働く意味」や、自らの適正、社風やそこで働く人々の価値観に深く触れることができます。アルバイトとしてではなく正社員として「働く」経験をするため、社会人としての基礎能力が身に付くことはもちろん、新社会人としての心構えも早い段階から行えることでしょう。
結論、日本でのインターンシップではなく、海外でのインターンシップの方が、本来のインターンシップの持つ目的を果たし、よりよいキャリア形成につながる機会となるといえます。
4:正解は海外インターン→日本でのインターン

海外でのインターンシップは、単なる異文化体験ではありません。それは、日本の企業が求める真のグローバル人材になるための強力なステップであり、その経験こそが、国内でのインターンシップや就職活動において、最大の武器となります。つまり、海外のインターンシップで得た力を、日本のインターンシップでの採用へとつなげるのが、賢いキャリア形成と言えるでしょう。
海外でのインターンシップでネイティブスピーカーと共に働く経験は、ビジネス英語、特にスピーキングとリスニング能力を高める絶好の機会です。この経験を通じて培われる実践的なビジネス英語力は、外資系企業はもちろん、海外展開を進める日本企業のインターンシップにおいても、即戦力となる強力なアピール材料になります。座学では決して得られない「生きた英語」を操る能力は、その後のインターンシップや就職活動において、大きな強みとなるでしょう。
さらに、外国人との交流や英語でのコミュニケーションに抵抗がなくなり、より柔軟性と適応力を持って仕事に取り組めるようになります。これは、多様なバックグラウンドを持つ人々との関わりが増えている現代のビジネスシーンにおいて、非常に価値のあるスキルです。本採用前のインターンシップで、グローバルな環境への適応力を存分にアピールできれば、採用担当者に強い印象を残すことができるでしょう。
また、海外でのインターンシップの経験は、他の応募者との明確な差別化にも繋がります。円滑なコミュニケーションをこなせるグローバルな人材であることは、採用に直結すると言われる日本のインターンシップで自己PRとして活用することができます。
その上、グローバル人材を積極的に募集している企業は、単に「良い大学を出ている」だけでなく、「自ら行動し、困難な環境でも結果を出せる」人材を求めています。海外インターンシップは、未知の環境に挑戦する主体性、言葉の壁や文化の違いを乗り越える問題解決能力、そして予期せぬトラブルにも諦めずに立ち向かう精神力など、学歴だけでは測れない内面的な強みを証明することができるプログラムです。
結論として、海外インターンシップでスキルと実践的な経験を積むことは、自身の市場価値を大きく高めます。 日本国内でのインターンシップに繋がるのはもちろんのこと、思い描く将来のキャリアを掴むための「最善の選択」となるでしょう。
5:世界有数のダイバーシティ オーストラリア・シドニーで開催される海外インターンシップ

アメリカ、カナダ、イギリスなどさまざまな主要英語圏が存在しますが、海外インターンシップ開催都市は、オーストラリア、シドニーです。
オーストラリアは国民約2,720万人(2024年6月時点)のうち、約3割にあたる約860万人が他国出身です。国籍も元々植民地支配をしていたイギリス系だけではなく、イタリア系や東欧系など様々な国籍から成り立つ非常にダイバー(多様性あふれる)な環境です。また、近年中国やインドを始めとしたアジア圏からの移民が増えており、アジアとヨーロッパを結ぶビジネス拠点となっています。
また、シドニーのあるニューサウスウェールズ州は、オーストラリア国内総生産の約30.7%を占め、オーストラリア企業の約33.6%がニューサウスウェールズ州を本社所在地としていると言われています。
シドニーは、多種多様な国が本社や主要拠点を構える国際経済都市です。同時に、多くの大学や専門学校もキャンパスを置き、重要な教育拠点でもあります。留学生に対する理解も他州他都市と比較してあり、留学生へのインターンシップに協力的な企業が数多くあります。だからこそ、インターンシップをするには最適な場所なのです。
参照:
Australia’s population by country of birth
Company registration statistics
Department of Foreign Affairs and Trade
6:海外インターンシップ参加者体験談【動画】
いかがでしたでしょうか。
近年、就職活動においてインターンシップが注目されていますが、日本の多くのインターンシップは「採用への近道」として位置付けられがちです。そのため、「ただ参加すればいい」と考えてしまったり、参加すること自体がゴールになってしまったりする学生も少なくありません。
しかし、海外インターンシップは、座学では決して得られない貴重な経験を提供し、大学での学びをより実践的なものへと深めます。これは、インターンシップ本来の目的である「職業体験、学習、そして企業における人材育成」という意義を強く体現しているからです。海外での経験は、日本の就職活動で優位性を築けるだけでなく、グローバルな視点と実践的なスキルを養う上でも非常に有効な手段と言えるでしょう。
将来のために、今、どこで、何を、どのように行動すべきか。しっかりと見極め、後悔のない未来を築くための一歩を踏み出すことが鍵となるでしょう。